Web3時代の社会基盤として注目を集めるNFT。 本記事では、国内の3つの先進事例を取り上げ、各事例の詳細な分析、インフラNFTが社会にもたらす価値と今後の展望について考察します。
この新しい技術がどのように私たちの生活を変え、より良い社会の構築に貢献できるのか、Web3時代におけるインフラの未来、そしてそれが私たちの暮らしにもたらす革命の可能性を一緒に探していきましょう。
インフラNFTの特徴
.jpg?fm=webp)
インフラNFTは、従来のインフラ資産(RWA)にNFT(非代替性)技術を適用した革新的な概念です。主な特徴は以下の通り。
- 唯一性と所有権の明確化:インフラ資産を唯一無二のデジタル資産として表現し、真正性を明確に証明可能
- 透明性と追跡可能性:ブロックチェーン技術を基盤とするため、取引履歴や所有権の移転が透明かつ追跡可能
- 分散化と安全性:非中央集権型の分散管理システムにより、データの改竄や損失のリスクが軽減される
- 付加価値の創造:従来は難しかったRWAを、簡易的なデジタルアセットとして表現。デジタルアートや仮想空間との連携により魅力的なコンテンツの創造に繋がる
- デジタル化によるコスト削減:管理や取引のプロセスがデジタル化され、効率化されます。
今回紹介する事例は価値の移転としてのNFTの流用ではなく、同技術を使うことで消費者のユーザビリティをより高めるコンテンツになったり、事業者側の作業効率を高めるためにWEB3技術を上手く活用するいったような、より実用的な内容になっています。
東京電力 電柱NFT
.png?fm=webp)
東京電力パワーグリッド(以下「東電PG」)は自社が展開している鉄塔、電柱などのアセットをNFTとしてコンテンツに落としこみ販売するだけでなく、インフラ整備の効率化を目的としたWEB3ゲームを展開するなど多角的に事業を行なっています。
一般的に鉄塔や電柱は地域の景観を崩すなどあまり好意的な見方をされることは少なく、
関心を持って接する機会があまりにも少ないため、東電PGは自社アセットをNFTとして販売することで、もっと身近に電力インフラを感じてほしいという想いがあるようです。.png?fm=webp)
出典:https://nft.hexanft.com/.png?fm=webp)
出典:https://nft.hexanft.com/
電力インフラ整備における課題
安定的に私達に電気を届けてくれている電力インフラ(送配電網)ですが、大きく分けると発電所から高圧の電気をマクロ的にエリア毎の配電網に供給するまでの送電網(鉄塔など)とエリア毎の施設に細かく供給する配電網(電柱など)に分類されます。.png?fm=webp)
出典:送電・配電の区分けと現在の費用構成(電力10社合計)(イメージ)
※電力・ガス取引監視等委員会 送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループ 中間とりまとめ(2018年6月)より抜粋
送電網と配電網はその大半が1970年代に建設されているため、現在老朽化による大幅な建て替えや大規模修繕の必要性が高まっており、これらの費用を捻出するための予算取りなど喫緊の社会課題として挙げられています。
身近な地域の電柱の事例でいうと、年々増えるカラスの巣作りによる停電リスクです。
カラスは主に電柱の上で巣を作るという習性があるのですが、巣の材料として使う針金などの金属が電線に触れることでショートし、停電を引き起こすリスクに繋がるのです。
そのため、作業員が定期的に巡回し、電柱の状態を確認しているのですが、東京電力エリアだけでも600万本以上ある電柱の1本1本を確認するのはかなり骨が折れる作業になります。
WEB3事業を通して提供したい価値
WEB3事業を通して提供したい価値は主に以下の通りです。また、5年、10年先を見据えた同社の新しい収益源としても見込んで活動されているようです。
【NFT、WEB3ゲームを展開する主な目的】
- 市民の電力インフラの維持管理に対する理解促進
- 老朽化や不足していくメンテナンス人材を補うためにインフラ整備の効率化
- 新たな収益源としてスケールする可能性があるか確認するためのPoC(実証実験)
電力インフラの課題と述べているように、市民の意識を無理なく上げるためにアプローチ方法の一つとして活用されているのがNFTやトークンをインセンティブとしたゲーム理論を取り入れた「ナッジ」(行動変容)による社会浸透です。
SNSを通して対象エリア内で必要な電力インフラの写真(電柱や換気口)の写真を撮影した人に対してポイントが付与され、ゲーム内で暗号資産にトレード可能のため、プレイヤーは適度に運動しながらインセンティブを獲得できるというメリットを享受することが可能です。
興味のある人は詳しいゲームの詳細は公式ページから一度確認してみてください。.png?fm=webp)
展望
現在東電ネットワーク内の自治体※1と連携して域内の電柱を対象に事業を展開していますが、今後は更にエリアを拡大して、事業を拡張されることが予想されます。
また、電力インフラNFTの販売は25年12月31日まで延長されているため、興味のある人はHEXAサイト※1から購入されてみてはいかがでしょうか。.png?fm=webp)
※1日本円だけでNFTの発行や売買ができる国内最大級のNFTマーケット
capture.x NFT
.png?fm=webp)
Capture.x NFTは、環境改善に貢献する設備やプロジェクトをデジタルツインとしてNFT化し、消費者と環境保護活動を繋ぐ革新的なプラットフォームです。
このサービスでは、ユーザーがデジタルオーナーとなり、対象施設にエールを送ることで、日々のCO2削減データを繰り返して確認できるとともに、「エールポイント」を獲得することができます。
一般的に企業や自治体による脱炭素に関する取り組み(主に太陽光などの再エネ電源の建設など)を通して行われるCO2排出削減の活動は対外的に発信はされていますが、市民には分かりにくい内容であること、実生活に直接的に関与することでもないため、馴染みが少なく、他人事になっていることが大半です。
capture.xの取り組みではこれらのCO2排出削減量を毎日目にする仕組みを提供し、脱炭素社会を自分事化する第一歩としてのきっかけ作りに関与しながら、2023年3月のローンチから1年半程で15万回以上の行動変革を実現したという成果も報告されています。
インフラ会社との取り組み事例として日本最大の発電事業社である株式会社JERA※2と連携し、同社の太陽光発電所をNFTとして販売中。.png?fm=webp)
※2:東京電力と中部電力の合弁による国内最大の発電事業社
太陽光発電NFTにおける課題
2011年の東日本大震災以降、日本では再生可能エネルギーの導入に力を入れています。
その中でも比較的発電コストが低い太陽光発電を中心に導入が進んでいる訳ですが、近隣住人から理解を得られないまま設置された発電所や、施工不良による自然災害時の2次被害(土砂崩れなど)の誘発、その土地の良き風景・景観を損ねるなど、SNSや一部メディアではマイナスに寄った意見が多く存在するのが実情です。
また、このようなマイナス意見を持っていない住人にしても実際どれほどCO2削減に貢献しているか、その実態を知るよしもなく、実際問題、発電オーナーや建設に関わった関係者以外には大々的に公表されていません。
このように断絶されている一般住民と、発電所オーナーの距離感を縮め、日々のCO2排出削減量を可視化、実際のエコアクションに繋げるためのきっかけを作るWEB3サービスがcapture.xです。
WEB3事業を通して提供したい価値
「行動変容の始まりはCO2排出削減量を見ることから始まる」ということでまずは日々のCO2の削減量を目にすることからスタートして少しずつ消費者のエコアクションをステップアップしていくことに注力されており、実際、同社サービスを利用する約8割のユーザーが同社アンケート調査の結果により、環境意識が高まり、日々の自身の行動を見直す機会になったと回答。
また、WEB3ならではのデータの透明性に着目して、ポイント還元量、寄付量の全体額、お金の流れ、スキームを開示し、透明性を担保したスキームでの運営を行うことで消費者を巻き込んだ形で脱炭素社会の実現を目指します。.png?fm=webp)
出典:capture.x.png?fm=webp)
日々のエールで溜まったポイントは、楽天ポイントに変換して同社サイトのお買い物時に利用できるため、賢く貯めて有効的に活用したいですね。
展望
直近では海外のメガソーラーNFTが販売されていたり、国内だけでなく海外プロジェクトにも目を向けているようで、太陽光NFTの種類もラインナップが順調に増えています。
また、太陽光だけでなく脱炭素に貢献するRWAであれば問題なくNFT化できるため、様々な設備がNFTとして販売されることが楽しみなプロジェクトです。.png?fm=webp)
▼詳細と購入はこちらのcapture.xストアから
https://www.capturex.world/stores
JR九州 NFT
.png?fm=webp)
JR九州NFTは、JR九州(日本鉄道九州)が2023年7月に立ち上げたデジタルマーケットプレイスプロジェクトです。このプラットフォームでは、ユーザーは主に以下のようなことを行うことができます。
- JR九州関連のデジタルグッズを購入する。
- 電車に乗ったり駅を訪れたりするとNFTがもらえます。
- NFTを将来の利益のために、または収集品として使用します。
この取り組みはJR九州のWeb3.0プロジェクトの一環であり、新たなデジタルマーケティング戦略の模索と顧客エンゲージメントの強化を目的としており、同社はNFTを現実世界の訪問者を引き付け、顧客にユニークな体験を提供する手段と捉えています。
NFTの利用をユーザーにとってより身近にするために、日本円での決済や交通サービス利用によるNFT取得など、NFTにあまり馴染みのない利用者であっても購入しやすいことが特徴です。.png?fm=webp)
出典:https://nft.jrkyushu.co.jp/
鉄道事業における課題
2019年のコロナ禍による人々のライフスタイルの変化や人口減少による、乗客数の低下が大きな要因になります。
民間企業として利益を追求しなくてはいけない中、乗客数の低下は大きな痛手になるため、コストを削減する観点で列車運行のダイヤ改正など着手を進められたようです。しかし、一部の乗客にとっては不便をかけてしまうという新たな課題や、コストを削るだけでなく売り上げを拡大していかなければいけないという問題に直面した結果、エリア外(国内の九州地区以外や、海外ユーザーなど)の顧客を獲得していくための施策としてWEB3事業を推進していく流れになったようです。
WEB3事業を通して提供したい価値
WEB3事業を拡大している主な理由は、顧客への新しいUX(顧客体験)の提供や、企業のマーケティング活動としての取り組みだけでなく、5年、10年先の鉄道事業の枠を超えた新たな収益源を見据えた大きな流れの取り組みのようです。
【WEB3マーケティングを通したブランド価値の向上】
- 新たな顧客接点の創出: メタバース空間、より多くの顧客層、特にデジタルネイティブ世代へのリーチを拡大
- デジタル・Web3.0技術の活用:顧客とのタッチポイントの拡大、新しい体験・価値・楽しみ方などの付加価値の創出
- 九州の魅力発信:「九州鉄道ランド」、JR九州の列車、駅、沿線の魅力を詰め込んだバーチャル空間の提供
展望
.png?fm=webp)
直近では世界最大規模のブロックチェーンメタバースを展開しているTheSandbox※3上に「九州鉄道ランド」を構築し、プレイヤーが様々なクエストをクリアしていきながら、街づくりに貢献していくWEB3ゲームになっています。
また、こちらのプラットフォームの運営にはJR九州が直接携わってるということからも、同社がWEB3事業に対してななり力を入れている事が伺えるでしょう。
近年メタバース上で土地を購入し、マーケティング活動を促進していく企業は年々増えていますが、Sandbox の利用自体が普及すればメタバース内の土地代も高くなり、PR効果が高まることから、メタバースを上手く使いこなす企業とそうでない企業では集客力に大きな差が生まれるかもしれません。
※3:イーサリアムブロックチェーンを基盤にした世界最大規模のメタバースプラットフォーム.png?fm=webp)
.png?fm=webp)
出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000029274.html
インフラNFTの可能性
.jpg?fm=webp)
NFTは、従来のインフラ資産管理に可能性を秘めた新しい概念です。
この技術は、物理的なインフラ資産をデジタル世界に融合させ、その価値やすべての権利を明確に証明することを可能にするだけでなく、インフラ資産の管理や取引に大きな変革がもたらされると期待されています。
経産省大臣官房Web3.0政策推進室の板垣和夏課長補佐の発言の通り、投機的な役割としてではなく、持続可能で社会課題を解決するようなサービスが求められています。
以下引用文
「持続可能で社会課題を解決するユースケースが多く出てくることは、ウェブ3の歩みを進める上で重要だ」
さらに、今後技術が進化していくことで、従来は困難であったインフラ資産の一部や流動的な取引を実現する可能性も秘めています。
これにより、より多くの人々がインフラ投資に参加できるように、資金調達の幅が広がることが期待されます。
一方でこの新しい技術には、法規制や整備技術的な問題、セキュリティリスクなど、まだまだ乗り越えるべき障壁が多数ありますが、これらの課題を一つずつ解決していくことで、NFTは社会基盤のあり方を大きく変える可能性を秘めているのです。
まずは、インフラ面での実用化が進み、都市開発やエネルギー管理、交通システムなど、様々な分野でのユースケースを生み出しながら、多くの顧客体験や付加価値を一人でも多くのユーザーに届けながら、インフラNFTの可能性を最大限に活かすことが今後の鍵となるでしょう。



 へいきょ
へいきょ Taku
Taku モリ
モリ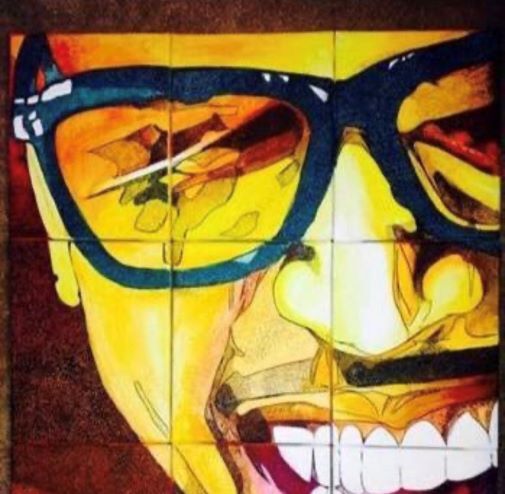 Melo.
Melo. KENNY
KENNY TAKUMA
TAKUMA localweb3運営
localweb3運営